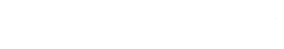リジェネラティブ・アーバニズムとは?環境再生型都市を解説
2025.02.10
近年の異常気象や大規模な災害は、人間の生活による環境破壊が原因だと考えられています。自然環境の恩恵を一方的に受け取ってきた私たちのライフスタイルは、これから先大きく舵を切らなければなりません。
これからの社会を考えるうえで、重要な視点となるのがリジェネラティブ・アーバニズムです。「リジェネラティブ(regenerative)」は英語で「再生させる」、「アーバニズム(urbanism)」は、建築学の言葉で「近代以降の都市計画全般」を指します。環境問題に対して根本的な解決策をとったうえで、自然環境と人間が末永く共存できる社会を目指す考え方です。
この記事では、リジェネラティブ・アーバニズムについて詳しくご紹介します。さらに、リジェネラティブな事業としてベトナム「Think Playgrounds」の事例を解説するので、ぜひご覧ください。
「リジェネラティブ・アーバニズム」とは
リジェネラティブ・アーバニズム(環境再生型都市)とは、人間と自然環境の共存共栄を目指す都市計画の考え方です。自然環境を修復・改善しながら、地球本来のシステムとともに私たち人間が生きられるような都市のデザインを目指します。
人間の暮らしや生産活動は、自然環境の恵みを享受することで成り立っています。生産活動に必要な資源や食糧、人間の生息に適した環境など、私たちが自然環境から得ているさまざまな恵みを「生態系サービス」といいます。
従来型の都市生活は、地球環境から生態系サービスを受け取って消費する一方通行のシステムです。ここ200年ほどの都市化・工業化による環境破壊は、生態系サービスの搾取ともいえるでしょう。近年の異常気象や地球温暖化などの環境問題は、生態系サービスを一方的に搾取しすぎた結果とも考えられます。
リジェネラティブ・アーバニズムでは、環境負荷の抑制だけでなく自然環境の修復・回復に重きを置きます。何が環境破壊を引き起こしているか、問題を根本から解決したうえで自然環境を再生する視点が特徴です。破壊された生態系や大気・水質汚染から自然環境を回復させる取り組みとして注目を集めています。
【参考資料】
リジェネラティブ・アーバニズムを求めて|一般社団法人 建築保全センター
生物多様性と経済活動|環境省
アーバニズムとアーバニスト|東京大学
リジェネラティブ・アーバニズムと災害対策

リジェネラティブ・アーバニズムは、気候変動によって起こる異常気象や台風・津波、地震などの自然災害に柔軟に対応するための都市計画でもあります。
これまでの災害対策は「災害時(または被災後)、現在の暮らしをどのように維持するか」に注目したものでした。リジェネラティブ・アーバニズムでは、災害からの回復力(レジリエンス)に重点を置いて都市をデザインします。自然災害の脅威そのものは受け入れたうえで、安全かつ速やかな対応ができるように柔軟な都市構造とシステムの構築を目指す考え方です。
この災害についての考え方は、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」にも関係しています。目標11のターゲットのうち、11-5「2030年までに、災害によって命を失う人や被害を受ける人の数、また、世界の国内総生産(GDP)に対して災害が直接もたらす経済的な損害を大きく減らす」は、まさに災害への柔軟な対応ができるか否かによって成果が変わる目標です。
また、11-a「国や地域の開発の計画を強化して、都市部とそのまわりの地域と農村部とが、経済的、社会的、環境的にうまくつながりあうことを支援する」は、リジェネラティブ・アーバニズムが目指すビジョンの1つだといえます。
2011年の東日本大震災をはじめ、日本でも毎年のように自然災害が起こっています。カリフォルニア大学ロサンゼルス校、東北大学災害科学国際研究所を中心とした国際共同プロジェクト「ArcDR3」は、リジェネラティブ・アーバニズムを軸に世界各国に共通の「新たな都市デザインの方法論」を見つける試みです。
ArcDR3は、2015年「第3回国連防災世界会議」で採択された防災アジェンダ「仙台防災枠組2015-2030」を踏まえて始動しました。東日本大震災の被災地の1つ・仙台で開催された国際会議から、災害への柔軟な対応ができる社会を目指す活動が始まっています。
【参考資料】
11.住み続けられるまちづくりを|公益社団法人 日本ユニセフ協会
リジェネラティブ・アーバニズム展―災害から生まれる都市の物語
特集 第3回国連防災世界会議の仙台・東北開催の概要について|内閣府
ベトナム・ハノイ「Think Playgrounds」の「冒険遊び場」事業
ベトナム・ハノイ発の「Think Playgrounds」は、ベトナム初の「冒険遊び場」事業に取り組む社会的企業です。ベトナム北部で現在開発中の「エコパーク」につくった子どもたちの遊び場を基軸に、ハノイがもつ社会課題や環境問題にアプローチしています。
ここでは、リジェネラティブ・アーバニズムとしてThink Playgroundsの事業をご紹介します。
冒険遊び場(プレーパーク)とは

Think Playgroundsの事業をご紹介する前に、まずは「冒険遊び場(プレーパーク)」について解説します。
冒険遊び場とは、1943年にデンマーク・コペンハーゲンで誕生した子どものための自由な遊び場のことです。冒険遊び場では、大人が事前に準備した遊びのプログラムや遊具・おもちゃのような既製品ではなく、子どもたちが自らの興味や願望によって自分で作り変える点を重要視しています。
子どもたちは、道具や工具を使って木や水、土、石などの自然素材や廃材で遊び道具や遊びそのものを作り出します。冒険遊び場は「これを作ったらどうなるだろう」「やってみたい!」という子どもたちの創造力を最大限に活かせる場です。日本では1970年代に導入、現在は全国で450団体以上が活動しています。
子どもたちの遊びを支えるため、冒険遊び場には「プレイワーカー」という専門スタッフが配置されています。早い段階から冒険遊び場に力を入れているイギリスでは、国家資格としてその専門性が認められている職種です。
【参考資料】
日本冒険遊び場づくり協会
冒険遊び場の専門性について|厚生労働省
やりたい! から始まるすべてのこと|日本プレイワーク協会
Think Playgroundsと子どもたちの「遊ぶ権利」
Think Playgroundsは、2014年に建築家チュ・キム・ドゥックとグエン・ティウ・クオック・ダットによって設立されました。人口密度が高く子どもの遊び場が少なかったハノイに、子どもたちの「遊ぶ権利」を尊重した冒険遊び場をつくるためです。
ベトナムは人口密度が高い都市が多い国として知られています。ハノイの人口は約800万人、2023年時点の人口密度は約2,556人/平方キロメートルです。加えて、緑地や公園の少なさが以前から問題となっています。Think Playground設立時の公園・緑地面積は市民1人当たり1.72平方メートル、大人1人が両手を広げて横になれる程度しかありませんでした。
また、ベトナムは近年急激に学歴重視の社会になりつつあります。自由に遊べる公園がないうえに高い学力を求められるようになり、社会全体で子どもたちの「遊ぶ権利」が軽視される傾向がありました。
Think Playgroundsは、国際交流基金の助成を受けて冒険遊び場事業を開始しました。遊び場づくりにあたり、東京で同事業に取り組む一般社団法人TOKYO PLAYを視察し、候補地選定や研修・実践指導などのサポートも受けています。
ベトナム初の冒険遊び場を開設した「エコパーク」は、ハノイ郊外で開発中のエコをテーマとした都市計画エリアです。東京ドーム100個分を超える500ヘクタールの面積をもち、冒険遊び場を含む4つの大きな公園を備えています。都市機能と自然を兼ね備えたエコパークに、Think Playgroundsは「子どもがつくる」「入場無料」「地域コミュニティも参加」の冒険遊び場を開設しました。
現在、Think Playgroundsは、エコパーク以外にも冒険遊び場・公園を増やしています。空間としての遊び場だけでなく、保護者へのセミナーやワークショップを通して遊びの重要性を伝える活動も開始しました。また、スラム街の環境改善やコミュニティ支援など、事業の幅を拡大しています。世界的にも評価されており、チュ・キム・ドゥックCEOはイギリスBBCが選ぶ「2020年度版 今年の女性100人」にベトナム人でただ1人選出されました。
【参考資料】
Think Playgrounds
ベトナム初の冒険遊び場~日本からの道のり~|日本冒険遊び場づくり協会
【報告】ベトナムにおける遊び場づくりを支援しました|日本冒険遊び場づくり協会
ハノイの環境問題と台風被害の再建にも取り組む

ハノイは、深刻な大気汚染問題を抱える都市でもあります。2025年1月時点のPM2.5濃度は1平方メートルあたり266μグラム、「世界の大気汚染都市リスト」の中でもワースト1位です。
人口密度の高さによって都市生活の中で排出される汚染物質が多いこと、工業分野による光化学スモッグ、農村部での手工芸品の生産活動や野焼きなどが主な原因です。さらに近年は、ハノイ郊外にある埋立処分場の容量逼迫によって、ゴミを屋外で焼却処分する住民が増えていることも問題視されています。
2020年、Think Playgroundsは「コミュニティ野菜タワーモデル」の実証実験を実施しました。高さ1メートルほどのタワー状の鉢を設置して植物を植え、生ごみをコンポスト化した肥料で育てる取組で、消費地での有機廃棄物処理、緑地増加、廃棄物焼却量の軽減が目的です。地域コミュニティの協力のもと、廃棄物処理と緑地の少なさを改善する新たな地域モデルの開発に取り組んでいます。
また、ハノイを含むベトナム北部は、2024年9月の大型台風「ヤギ」で大きな被害を受けました。特に、ハノイ市内を流れるホン川の中州にある「バナナ・アイランド(Bai Giua)」の住民やその周辺の「浮き家」に住む人々の被害は深刻です。Think Playgroundがバナナ・アイランドで作ってきた遊び場や庭園・公園も水没しました。
Think Playgroundsは、地域住民の居住空間と遊び場・公園の再建に取り組んでいます。バナナ・アイランドの被害状況調査に加え、地域コミュニティの協力のもと公園の清掃や遊具の修理・修繕、施設の整備を行っています。子どもたちをはじめ、地域の住民が安全に身体を動かせる場を再建し、心身の健康を回復することに重点を置いた活動です。
【参考資料】
ベトナム安全対策基礎データ|外務省
vietnam2020|公益財団法人公害地域再生センター
vietnam2024.2|公益財団法人公害地域再生センター
THINK PLAYGROUNDS! SPECIAL NEWSLETTER 台風ヤギと歴史的被害の洪水|一般社団法人TOKYO PLAY
まとめ
リジェネラティブ・アーバニズムについて、ベトナム・ハノイの「Think Playgrounds」を例に挙げながらご紹介しました。
自然環境を修復・改善しながら、本来のシステムで私たち人間が末永く生きていける都市をデザインする、いわば「人間と自然の共存共栄」がリジェネラティブ・アーバニズムが目指すビジョンです。これからは、自然環境から一方的に受け取るだけだった恩恵をお返ししつつ、私たち人間もよりよく生きられる仕組みをつくる必要があります。
ご紹介したThink Playgroundsの事業は、緑地増加やアップサイクル使用という面だけでなく、すべての人間が本来のシステムで健やかに暮らせるまちづくりという点でもリジェネラティブな事例です。冒険遊び場事業に取り組む団体は日本にも400以上あるので、興味が湧いた方はぜひ調べてみてください。
(ライター:佐藤 和代)
〈関連記事〉
「リジェネラティブ」とは?サステナブルを超える企業の取組