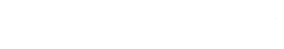リジェネラティブ・デザインとは?基本的な考え方と企業事例
2025.02.13
「SDGs」「ESG経営」が社会に浸透しつつある現在、新たに注目されているのが「リジェネラティブ」です。英語の「regenerative(再生可能な)」に由来する言葉で、自然環境や社会を「再生させる・今よりもよい状態にする」という発想の考え方を指します。
異常気象や大規模自然災害が続き、現在の地球環境が危機に瀕していると多くの人が感じとっているでしょう。この記事では、従来型の「エコ」より1歩先に進んだ「リジェネラティブ・デザイン」を解説します。日本企業が取り組んでいるリジェネラティブ・デザインの事例もご紹介するので、ぜひご一読ください。
リジェネラティブ・デザインとは
「リジェネラティブ・デザイン」とは、すべての生物にとってより良い状態を目指したデザイン・設計の在り方です。企業が自社商品・サービスを開発するとき、または地方自治体・行政がまちづくりや都市計画を行うときなどに、「自然環境の再生・回復」という視点からデザインを考えることを指します。
商品・サービスが「環境に優しい」「エコ」という場合、これまでは「環境への負荷が少ない」ことを意味する場合が多いものでした。「リジェネラティブ」は、ただ単に環境負荷を減らすだけでなく、自然環境を積極的に「再生させていく」という考え方です。商品・サービスを通して、現状よりも豊かな自然環境を目指すことが「リジェネラティブ・デザイン」といえます。
では、商品・サービスが「リジェネラティブ」であるには、どのように設計する必要があるのでしょうか。アメリカの大手デザイン会社HDRは、リジェネラティブ・デザインについて次の6つの基準を提唱しています。
① エネルギー・水・廃棄物の「ネットゼロ(実質ゼロ)」
② 製品ライフサイクルの「カーボンニュートラル」
③ 消費者の健康と福祉につながる快適な環境づくり
④ 無害で透明性のある材料
⑤ 再利用・回復可能で耐久性が高いこと
⑥ すべての人が平等に使えるデザイン
HDRの基準を見ると、リジェネラティブ・デザインでは「自然環境」と「私たち人間」のどちらにもよい影響を与える視点が重要だとわかります。二項対立ではなく、人間を含めた生態系・自然環境をよくしていくという考え方です。
リジェネラティブ・デザインは1970年代に生まれた概念ですが、1990年代以降改めて注目されはじめました。特に、イギリスの建築家マイケル・ポーリンの活動が代表的です。
【参考資料】
リジェネラティブ・デザインの実践をめぐることはじめ|一般社団法人 建築保全センター
6 Things to Know About Regenerative Design | HDR
自然の叡智から学ぶ「バイオミミクリー」

リジェネラティブ・デザインでは、商品・サービス設計の際に生態系のシステムや仕組みからヒントを得ます。「自然の生態系を模倣し、連携する」点が大きな特徴です。
従来「環境に優しい」「エコ」といわれてきた商品やサービス、建築や都市計画は、注意深く見ると「人間が主体」であるケースも多いです。CO2排出量の削減やエネルギー効率の向上ができたとしても、人間主体でデザインされたものには「自然環境はコントロールするもの」という発想があります。いくら「環境に優しい」といえるものでも、本質的に地球環境や生態系に適していない可能性は捨てきれません。
リジェネラティブ・デザインの「自然の生態系を模倣し、連携する」という考え方は、「バイオミミクリー」ともいいます。ギリシャ語の「bios(生命)」と「mimesis(模倣)」を組み合わせた造語で、自然界にあるデザインやシステム、生態系から学び、模倣してより持続可能なイノベーションを起こすことです。「どのように自然をコントロールするか」ではなく「人間をどのように自然界に適合させるか」という視点で考えます。
国内では、新幹線500系の事例がよく知られています。新幹線の開発開始当時、車体から突き出た「パンタグラフ」によって起こる騒音が大きな問題でした。そこで、開発チームは鳥類の中でも最も静かに飛ぶフクロウの羽からヒントを得ました。フクロウの羽の仕組みをパンタグラフに取り入れたことで空気抵抗が減り、騒音を約30%カットすることができたのです。
また、カワセミの鋭いくちばしの形状を新幹線のデザインに活かしたことで、走行抵抗や騒音、消費電力を大幅に低減することができました。自然界のデザインを注意深く観察して、学びを得た結果がよく現われている事例です。
【参考資料】
What is biomimicry?|一般社団法人バイオミミクリー・ジャパン
自然界に学ぶ最先端の技術|セブン・イレブンみどりの基金
地球の限界 “プラネタリーバウンダリー” & 循環型社会~世界と日本の取り組みからみんなでできることを考える|国立環境研究所
ヤマハ発動機・株式会社船場「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab」
リジェネラティブ・デザインの国内事例として、本記事では株式会社船場によるヤマハ発動機株式会社の共創スペース「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab」をご紹介します。
ヤマハ発動機のYAMAHA MOTOR Regenerative Lab(通称:リジェラボ)は、新事業やイノベーションを生み出す拠点として2024年10月にオープンしました。情報発信や交流ができるワークショップエリアや、社員や来訪者が使えるコワーキングエリア、ギャラリーやキッチンスペースを備えた複合型施設です。
ヤマハ発動機は、世界トップシェアを誇るバイクを筆頭に、幅広い領域での製造事業で知られています。リジェラボには、ヤマハ発動機が自社事業を通して取り組んできたさまざまな社会問題について発信するという役割もあります。
ヤマハ発動機の事業内容や実績、理念をデザインとして具体化し、リジェラボという空間を作り上げたのが東京都港区の株式会社船場です。船場は、リジェラボの設計・施工、屋内の什器や家具、アートワークなどの制作を担当しました。リジェラボでは、訪れた方に什器やアートワークのストーリーを説明し、リジェネラティブについて考えるきっかけを提供しています。
【参考資料】
ヤマハモーター リジェネラティブ ラボ:リジェラボ(横浜共創スペース)|ヤマハ株式会社
船場、ヤマハ発動機由来の廃棄物をアップサイクルし、リジェネラティブを考える共創スペースを創造|PR TIMES
リサイクルが難しい「FRP」をアップサイクル

リジェラボのなかでも、ヤマハ発動機の製品製造・輸送過程で生じた廃棄物をアップサイクルした什器は、空間のテーマ「リジェネラティブ」の象徴といえます。
ヤマハ発動機では、FRP(繊維強化プラスチック)を使って、レジャーボートやプールなどさまざまな製品を製造してきました。プラスチックにガラス繊維や炭素繊維を混ぜ合わせたFRPは、耐候性・耐震性に優れていますがリサイクルが難しい素材です。ヤマハ発動機では可能な限りのリデュース・リユース・リサイクルを施しながら、FRPの製造やリサイクルの技術研究を進めてきました。
ヤマハ発動機の取り組みを受け、船場は廃棄予定のFRP製競技用プールをアップサイクルして展示用什器を制作しました。什器はプール裏面の構造体のフォルムを活かしたデザインで、両壁面にはベンチを作りつけています。また、リジェラボ内の可動棚やホワイトボード、テーブルの天板もFRPをアップサイクルしたものです。
従来、廃棄されるプールは同じくプールとしてリユースされるのが常でした。リジェラボの展示用什器は、新しい再活用方法としても注目されています。
ヤマハ発動機は、1974年に日本初のオールFRPプールを製品化した企業です。20メートル以上の学校用プールは、国内でもトップシェアを誇っています。2024年3月末にプール事業から撤退したものの、リジェラボの什器には「使い終えた後のことまで考えたものづくり」という視点が具現化されています。
【参考資料】
「資源循環」への取り組み|ヤマハ発動機株式会社
YAMAHA MOTOR Regenerative Lab 家具・什器 |株式会社船場
FRP船リサイクルシステムの運用について|国土交通省海事局
船場の「未来にやさしい空間づくり」

株式会社船場は、オフィスや店舗・大型商業施設、ホテルなど幅広い分野の空間づくりに取り組んでいる企業です。アップサイクルやアートワーク制作など、さまざまな手法を用いたエシカルな空間創出が特徴で、内装業界におけるエシカルデザインのフレームワーク「Circular Renovation®︎(サーキュラー・リノベーション)」を提案しています。
建築・内装業界では、長年主流となっている「スクラップアンドビルド方式」によって、短期間で廃棄物が大量排出される現状が問題とされてきました。例えば、環境省「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書」によると、令和4年度の建設業における産業廃棄物は8,017万トンです。これは産業廃棄物全体の約21%にあたります。
「ゼロウェイストな空間づくり」を目指し、船場は2020年に「ゼロウェイスト推進室」を設立しました。施工・解体現場での廃棄物分別、混合廃棄物の削減を徹底した結果、2024年の施工案件の「1次リサイクル率」は平均94%に達しています。
船場の公式ホームページでは、自社のエシカルデザインについて「サプライチェーン全体で未来にやさしい空間を共創すること」と表現しています。続く「人や地域社会、自然環境への”おもいやり”の視点を持った空間づくり」は、まさにリジェネラティブ・デザインの根幹にある視点です。自然環境に配慮するだけでなく、現代日本が抱える少子高齢化や人権問題への対応、多様性を真に認め合える社会づくりと向き合った空間デザインを目指しています。
また、船場ではデジタルデザインを活かしたエシカルな空間づくりにも挑戦しています。先にお伝えしたように、「リジェネラティブ」は単に「環境に優しい・自然志向」だけではありません。ICT・AIの実装、地域エコシステムの再生などのデジタルソリューションは、これからのリジェネラティブ・デザインにも必要不可欠な存在です。
【参考資料】
株式会社船場
エシカルデザイン |株式会社船場
船場、建設廃棄物の分別を徹底し、内装工事における1次リサイクル率平均94%を達成|株式会社船場
令和5年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和4年度速報値(概要版)|環境省
まとめ
リジェネラティブ・デザインの基本的な考え方と、国内企業の事例をご紹介しました。
「リジェネラティブ」というと耳慣れない方も多いかもしれませんが、例えばバイオミミクリーの例としてご紹介した新幹線500系「のぞみ」の走行開始は1997年のことです。リジェネラティブ・デザインの根本にある「自然の叡智から学ぶ」という発想は、意外と身近なところで発見できるかもしれません。
「すべての生物にとってより良い状態を目指す」リジェネラティブ・デザインは、「人間が地球環境とより仲良くできるデザイン」とも言い換えられます。異常気象や自然災害が重なると、どうしても「人間と自然は相容れないもの」と考えてしまいがちです。人間が自然の一部として生きていくために、今こそリジェネラティブ・デザインが求められています。
(ライター:佐藤 和代)
〈関連記事〉
「リジェネラティブ」とは?サステナブルを超える企業の取組
リジェネラティブ・アーバニズムとは?ベトナム企業の取組事例を解説