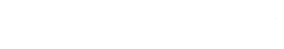サステナブルツーリズムの先へ!リジェネラティブな観光とは
2025.03.14
コロナ禍を経て、世界、そして日本の観光業が回復している今、環境を考慮したよりよい観光のかたちが模索されています。エコツーリズム、サステナブルツーリズム、レスポンシブルツーリズムとさまざまな観光スタイルが現れるなか、特に活発化しているのが「リジェネラティブツーリズム」です。今回はリジェネラティブツーリズムについて解説しながら、国内事例を取り上げます。
サステナブルツーリズムとリジェネラティブツーリズムの違いとは?
「リジェネラティブツーリズム」とは、旅行者が旅行先に着いたときより、旅行先を去るときのほうが、よりよい状態になっていることを目指す観光スタイルです。「再生型観光」「リジェネラティブトラベル」とも呼ばれます。
「リジェネラティブトラベル」と比較されるのが「サステナブルツーリズム」です。「サステナブルツーリズム」は、旅行先の環境や文化、社会、経済の側面から地域の持続性を求める、持続可能かつ発展性のある観光を目指したものです。
「リジェネラティブツーリズム」は、観光業が新型コロナウイルスでパンデミックを受けた状況のなかで、将来の観光業の方向性を示すものとして注目を浴びました。
2020年には、六つのNPOにより「Future of Tourism」連合が設立されます。リジェネラティブツーリズムには言及していませんが、「公平な所得分配を要求する」「量より質を選ぶ」「観光の負荷を軽減して地域社会や環境にポジティブなインパクトをもたらす」など、将来の観光を見据えた13の基本原則を策定し、旅行会社や観光地の自治体など約600機関が署名(2021年9月時点)しています。
【参考資料】
「持続可能な旅」がその座を譲る 「再生を後押しする旅」の時代が来た|朝日新聞社
About the Future of Tourism Coalition|The Future of Tourism Coalition
リジェネラティブツーリズムの国内事例
ここでは、旅先のアクティビティを通して地域をよりよく回復・再生する国内の事例を取り上げます。
リジェネラティブツーリズムを展開する宿泊施設「楽土庵」 |株式会社⽔と匠
富山県砺波(となみ)市にある散居村(さんきょそん)の保全・継承を目的として、株式会社⽔と匠が運営する宿泊施設「楽土庵 (らくどあん)」では、リジェネラティブツーリズムを手がけています。
散居村には、⾃然と共⽣しながら積み重ねてきた景観や伝統の⼿仕事・⽂化といった地域資源が残っています。しかし、ライフスタイルの変化により⽣活の中で維持や活⽤が難しく、地域住⺠がその価値を客観的に評価していないために、景観の保全や伝統の継承が困難な状況に直面していました。
楽土庵では宿泊代金の2%を散居村の保全活動団体へ寄付し、散居村の保全や文化継承に寄与しています。カイニョ(屋敷林)の整備を行い、その剪定枝を木質バイオマス発電に利用する活動や、カイニョの落ち葉から腐葉土を作る活動を支援することで、カーボンニュートラルにも貢献します。
また楽土庵は、散居村の回復と再生のためのさまざまなアクティビティも展開。富山の伝統的な絹織物「しけ絹」を製造する⼯房で作り⼿の思いにも触れることのできる絹織物⼯房訪問や、標⾼差400mをパラグライダーで⾶⾏し、散居村の景観を空から眺めるパラグライダー空中散歩、作務⾐に着替えて書道家でもある光圓寺の住職に学ぶ静謐な寺院での書道体験などが行われています。

母体である⼀般社団法⼈ 富⼭県⻄部観光社 ⽔と匠では、地域内外の⼈が一緒になって散居村の保全に取り組むナショナル・トラスト運動を見据えます。交流拡⼤を目的に、ブログ、ポッドキャストなどを継続的に発信し、地域に共感してくれる⽅を内外から募りながら散居村保全に取り組むためのプラットフォームの整備にも力を入れています。
散居村での取り組みを通して、散居村では地域住⺠が⾃主的・主体的に地域保全・再⽣に取り組む機運が向上。地域の持続性向上のための新たな事業やビジネスの種が芽吹き始めていると報告されています。
【参考資料】
散居村ウォーク|楽土庵
体験 リジェネラティブ アクティビティ|楽土庵
旅⾏者が「草原の守り⼈」となる草原保全アクティビティ|阿蘇カルデラツーリズム推進協議会
熊本県阿蘇(あそ)市にある「千年の草原」は千年にわたって⼈と⾃然が共存共栄してきた大草原です。年間を通して多くの人が訪れる観光スポットでもある一方、農業形態の変化や担い⼿の⾼齢化などで草原を維持しづらいという状況でした。
熊本県が行った2016年の調査で、30年後には約6割の草原が失われるかもしれないという可能性が示されました。環境省による自然再生プロジェクト「阿蘇草原再生」では、阿蘇草原30年後の目標に「今(2021年)と変わらない規模の阿蘇草原を残す」を掲げています。
それだけでなく、草千⾥などの観光スポットではオーバーツーリズムが発生。通過型といった観光が主で経済効果も限定的という課題も抱えていました。
そこで立ち上げたのが、旅⾏者が「千年の草原」の保全活動に参加して「草原の守り⼈」として地元農家とともに草原を守り、楽しみ受け継ぐリジェネラティブなコンテンツです。そのほか、オーバーツーリズムや通過型観光への対応策として、早朝やナイトタイムなどを活⽤した草原滞在コンテンツもスタートしました。
観光と農業と環境の好循環をまわすことを目的にしたこれらのアクティビティは、大きく3つに分けられます。どれも普段は⽴ち⼊ることのできない草原内で体験ができるものばかりです。
まず「Regenerativeコンテンツ」では、旅⾏者が茅刈りや防⽕帯づくりなどの草原保全活動に参加。終了後は地元農家とあか⽜BBQを囲み交流を深めることで、阿蘇の草原への共感や愛着を⾼め、草原を守り、楽しみ、受け継ぐことにつなげる取り組みです。
2つ目の「Off the beaten trackコンテンツ」では、早朝の⽇の出や雲海、夜間の星空を草原内で鑑賞し、地元⾷材のフード、ドリンクを楽しむことができます。
3つ目は「Universal tourismコンテンツ」で、自動車に乗車しながら草原を⾒学し、ガイドの説明を受けて阿蘇の歴史や⽂化などを知るアクティビティです。これまでE-Bikeで実施していたアクティビティが⾼齢者など利用者を限定せずに楽しめるユニバーサルなコンテンツとして展開されています。
もともと草原の保全活動は、地域住⺠によって⾏われてきたものです。この基盤を活⽤しながら、草原を観光に活⽤するための草原活⽤ガイドラインを遵守したうえで、旅⾏者が「草原の守り⼈」として草原保全活動に参加できる仕組みを構築しました。
コンテンツで得た収益の⼀部は草原保全料として地元の組合に還元。草原保全料の還元額は令和5年度は40万円にのぼり、令和6年度は250万円を目指します。
そのほか、道の駅などで農畜産物を旅⾏者が購⼊できる場を設けることで消費拡⼤を促進。農畜産物や草原由来産品の消費拡⼤、ガイドの所得向上などにつなげます。
本取り組みを通して、旅⾏者は草原でリフレッシュし、農家(地元の組合)は草原保全料の還元を受け、環境⾯では希少な動植物が保全されるという三⽅良しの好循環をつくり、阿蘇の草原の減少に⻭⽌めをかけています。
【参考資料】
サステナブルな観光に資する好循環の仕組みづくりに向けた事例集|観光庁
阿蘇草原再生~子どもたちへ引き継ぐ千年の草原~|環境省 自然再生プロジェクト

旅行者が日常を離れて滞在を楽しむことができて、地域と自然がより豊かになる。そんなプラスの影響が生まれるように働きかけるリジェネラティブツーリズムは、これから確実に加速していくと考えられています。
リジェネラティブツーリズムのヒントになるのが地域課題です。環境問題を含め自然循環の一部を担うことが多い地域課題を、新たな視点で捉え直してみませんか? それがリジェネラティブツーリズムへの一歩につながるのかもしれません。
(ライター:藤野あずさ)
〈関連記事〉
SDGsに貢献する観光業の事例 旅でカーボン・オフセット
新しい旅の常識になる?「レスポンシブル・ツーリズム」のパラオの事例を紹介