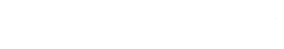日本のリジェネラティブ(環境再生型)農業 脱炭素に貢献
2025.02.19 これまで私たちの食を支えてきた農業は、大量の温室効果ガスの排出、農地への転換による森林破壊、農薬使用による土壌や海洋の汚染など、多くの問題を抱えています。特に、農業により排出される温室効果ガスは世界の約4分の1を占め、農業が及ぼす影響の大きさは深刻です。
これまで私たちの食を支えてきた農業は、大量の温室効果ガスの排出、農地への転換による森林破壊、農薬使用による土壌や海洋の汚染など、多くの問題を抱えています。特に、農業により排出される温室効果ガスは世界の約4分の1を占め、農業が及ぼす影響の大きさは深刻です。
こうした問題に確実にアプローチできる手法として「リジェネラティブ農業」に期待が集まっています。「耕さない農法」を用いて土壌を再生することから「環境再生型農業」とも呼ばれます。
「リジェネラティブ農業」は、炭素を吸収(隔離)する脱炭素型、かつ土壌再生の観点から世界的に注目を浴び、特にアメリカで取り組みが進んでいます。日本では始まったばかりですが、日本とアメリカでは風土や栽培の規模が大きく異なるため、アメリカの「リジェネラティブ農業」をそのまま日本に導入するのは難しいという意見もあります。
そこで今回は、国内で先駆的に取り組まれている「リジェネラティブ農業」にフォーカスし、具体的な実践例を見ていきましょう。
リジェネラティブ農業とは?
リジェネラティブ農業は「環境再生型農業」とも呼ばれ、土壌を修復・改善して、自然環境の回復につなげることを目指しています。
主な特徴は次のとおりです。
・不耕起栽培
畑を耕さずに作物を育てる農法のこと。土壌を掘り起こさないことで、土壌侵食が減り、土壌は水分や有機物を多く含むようになります。炭素を多くとどめ、温暖化対策にもつながります。
・被覆作物の活用
栽培時期の合間の、農地を休ませておく時期に、被覆作物としてアルファルファやクローバー、ソバなどを育てます。被覆作物が炭素を土壌に隔離し、土壌有機物を増やします。
・輪作
同じ土地で種類の違う作物を、一定のサイクルで周期的に変えて栽培すること。土壌の栄養分が欠けるのを防ぎ、病気や害虫の発生を抑えます。
・合成肥料の不使用
合成肥料ではなく有機肥料を使用することで土壌環境を守り、土壌を改善します。
近年、世界的に活発な動きを見せるリジェネラティブ農業は、先住民の知恵と実践から生まれた農法に基づいています。日本の場合、不耕起栽培は以前より行われていた農法で、小規模な田畑で実践されてきました。
地球環境と私たちの健康を守るためにも、古くから続けられてきた農法を頼りに、現在に適合した技術へ展開することが求められています。
【参考資料】
why-regenerative-organic?|Regenerative Organic Alliance
なぜ、不耕起栽培なのか?

リジェネラティブ農業の最大の特徴は、不耕起栽培であることです。どんなメリットがあるのでしょうか?
「“耕さない”ほうが土の生物多様性が高まる」と話すのは、土壌生態学者で環境配慮型の農業の研究と実践に努める福島大学の金子信博さんです。WWFで行われた生物多様性スクール2023 第5回「生物多様性と農業~土と水から考える」で、次のように語っています。
「有機農業で、耕す場合と耕さない場合を比較した実験では、耕さないほうが土壌炭素が増え、有効態のリン濃度が高くなり、土が良くなりました。また土壌動物が20倍にも増えました」
実験では収穫量にほぼ差がなかった、という結果も出ています。また、この不耕起栽培は国連食糧農業機関(FAO)が推奨する環境を保全する農法の一つです。不耕起栽培は世界の農地の約12.5%で行われる一方、日本ではまだ進んでいない現状があります。
「耕さない農業は土壌に炭素やメタンなどの温室効果ガスを吸収し、水はけがよくなることで強い雨にも対応できるとされています。土壌を保全する農法を推進することで、生物多様性の保全と気候変動対策につながります」
【参考資料】
生物多様性スクール2023第5回 農業 土と水から考えるー新しい農業への転換は始まっている!|WWF
リジェネラティブ農業の国内事例3選
Three little birds合同会社
「Three little birds」は、ソーラーシェアリングのもと、有機農業で生産しながら、地域再生の観点から商品開発やエコツアーにも取り組む会社です。
ソーラーシェアリングとは、太陽光パネルのもとで耕作を行う環境配慮型の発電方法を指し、「営農型太陽光発電」とも呼ばれます。
太陽光発電の売電収入を得られるため、有機農業で収益の確保が難しい品目でも営農が可能です。地域の耕作放棄地などを活用し、ソーラーシェアリングのもとで大豆を栽培してきました。
「Three little birds」は、2021年に大豆の不耕起有機栽培をスタート。3年目の2023年には、これまでの試みをもとに、試作除草機のさらなる改良、播種直後から作物を植えつけた列の間の除草を高頻度で実施、大豆栽培の前にムギを育てる輪作体系の導入、などを徹底。こうして栽培された大豆の収量は、全国や千葉県の平均と比べると同等以上の実績を得ることができました。
それだけでなく、ソーラーシェアリングと不耕起栽培で土壌再生を目指す「Three little birds」のフィールドでは、エシカルな教育や不耕起栽培の畑での草取り体験会などが行われ、学びの場にもなっています。
【参考資料】
Three little birds 合同会社
Three little birds 合同会社~ソーラーシェアリング×オーガニック特産品による農の再生~|農林水産省
土壌再生をめざす大豆|パタゴニア

はちいち農園
「はちいち農園」は2017年より不耕起栽培を実践し、2018年に神奈川県茅ヶ崎市にて就農しました。 無農薬、無化学肥料、 無動物性堆肥による不耕起栽培を実践。畑の草や微生物、菌などの働きを活かしながら、多種多様な生命が循環できるようにと、耕運機など動力機械を使わない手作業による農業を行っています。
「はちいち農園」では、苗のそばに被覆植物(カバークロップ)を施してCO2を貯留し、土壌を耕耘しないことでCO2排出量をできるだけ抑えます。これは生物多様性や土壌を再生しながら生産性も向上させることが不耕起栽培に取り組む目的の一つと捉えているためです。
さらに「はらいち農園」では不耕起栽培をとおしてカラダの再生、ココロの再生も掲げます。工業畜産由来の動物性堆肥や化学肥料はもちろん、殺虫剤、除草剤なども全く使用しない理由は、食べる人の健康と環境を思う優しい心の再生があるためです。
また、2023年には不耕起栽培で育てた大豆を主原料としたアイスクリーム「SOYSCREAM!!!」の製造・販売を開始。この背景には、収量不足などさまざまな課題に直面することが多い不耕起栽培の農家の現状があります。こうした農家を支援し、農地面積を増やすための後押しができれば地球温暖化の緩和にもつながると考え、商品化に至りました。
今後は、「SOYSCREAM!!!」との提携農家を現在の3農家から13農家へ増やし、関係する不耕起栽培の畑を500アールから1,000アール(100,000平方メートル)へ広げることを目標に掲げています。次年度以降は各農家の土壌炭素貯留量などの測定も実施し、圃場データ公開によるソーシャルインパクトの数値化と可視化にも取り組む予定です。
【参考資料】
はちいち農園
大豆のアイスクリームを食べて不耕起栽培の畑を増やし、地球を冷やそう!|PR TIMES
SHO Farm
神奈川県横須賀市にある「SHO Farm」は「千年続く農業」を掲げ、無農薬・無化学肥料に取り組む農園です。
2014年、有機農業の農園として夫婦でスタートし、2022年からはすべての畑で不耕起栽培を取り入れました。国内で実践例やノウハウが広まっていないなか、肥料には緑肥(土にすき込み肥料にするために栽培する作物)を使い、畑を耕さず除草も極力行わない農法で、少量多品目の野菜と果物を生産しています。
トラクターは使わず、ニンジン収穫後はライ麦の種を蒔いて草をかぶせるなど、緑肥で畑を覆うことで、畑の土壌表面の露出を避け、土壌生物と植物の根のネットワークを絶やさないことを大切にしています。
農園の建物には、ソーラーパネルと蓄電池を設置し、農機具の充電もまかないます。キッチンやストーブの熱源には薪を使い、雨水も活用。できるだけエネルギーを自給します。
そのほか、野菜セットの値段を購入者自身で決められる「Pay It Forward」という仕組みを導入している点も特徴です。野菜セット購入の際、正規の値段よりも多く支払った人の分だけ、他の誰かが安く野菜セットを購入できます。これはSHO Farmの農園主が「お金に余裕がない」状態のつらさを経験した過去から、極端な格差社会に強い問題意識を持ち、仕組み化されました。
【参考資料】
SHO Farm
農園のアクティビスト|パタゴニア
 日本のリジェネラティブ農業の事例は少ないですが、熱量の高い実践者が先駆的に取り組む事例から、リジェネラティブ農業がこれからの地球環境を再生させる有効な手段になると感じました。
日本のリジェネラティブ農業の事例は少ないですが、熱量の高い実践者が先駆的に取り組む事例から、リジェネラティブ農業がこれからの地球環境を再生させる有効な手段になると感じました。
土の健康や土壌保全への関心が高まるなか、日本の風土に合った不耕起栽培が広がることに期待します。
(ライター:藤野あずさ)
〈関連記事〉
リジェネラティブな海外事例「アグロフォレストリー」
「リジェネラティブ」とは?サステナブルを超える企業の取組