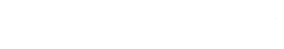コンポストで生ごみを活用!企業・農園のリジェネラティブな取組
2025.02.22
「コンポスト」は多くの人にとって聞きなれた言葉ではないでしょうか。近年ではおしゃれな道具も販売され、コンポストの実践者も増えているようです。
生ごみや落ち葉を「堆肥」という資源へ変えるコンポストは、家庭や企業活動から出る生ごみを減らし、廃棄物削減に役立つだけではありません。生ごみの輸送や焼却時に発生するCO2を減らし、気候変動への対策につながります。
さらにコンポストで作られた自然由来の堆肥は、土壌の有機物や保水力を回復・再生させることから、環境を再生させる「リジェネラティブ農業」へのアプローチになります。
この記事では、コンポストの仕組み、メリット・デメリットを解説しながら、企業や農園の事例を取り上げていきます。
コンポストとは
コンポストとは、微生物の力によって生ごみや落ち葉などの有機物を分解させて作った堆肥のこと。日本では、堆肥をつくるための容器をコンポストと呼ぶ場合が多いです。
日本において、コンポストは昔から各家庭で行われており、明治末期ごろまで生ごみやし尿から肥料を作り、土に還す農業を行っていたことがわかっています。
では「堆肥」はどのように作られるのでしょうか? 堆肥づくりの主役は微生物です。容器に入れられた生ごみが、土中にいる微生物の「発酵・分解」の働きによって堆肥へと変化していきます。完全な堆肥になるまで数ヶ月かかりますが、これは微生物の働きかけが緩やかなためです。
家庭などから出る生ごみは有効活用すれば、ごみの回収に出す必要がありません。堆肥化によって、生ごみを土に還すという資源の循環を生み出すことができます。
【参考資料】
コンポストとは? メリットや種類ごとの特徴、家庭での始め方を解説|朝日新聞デジタル
コンポストとは?|岡山県笠岡市

メリット
コンポストの活用には、環境問題といった社会課題の解決などさまざまなメリットがあります。
・生ごみが減る
生ごみをごみとして出さずにすむため、生ごみの排出量が減り、食品ロス削減につながります。また、約8割もの水分を含む生ごみは、輸送や焼却にかかるコストが大きいという問題も抱えています。自治体や企業が費用を負担する現状、生ごみを削減できれば処理にかかるコスト削減も実現できます。
日本では今、生ごみを燃やしたあとの灰を埋め立てる最終処分場が不足しています。生ごみの活用はその解決策になるうえに、ごみとして捨てるのに必要なビニール袋も削減でき、プラスチックゴミを減らすことができます。
・CO2排出量を削減できる
水分を多く含む生ごみは、燃やすために石油など多くのエネルギーを消費します。コンポストで堆肥化すれば、燃やす量が減るためCO2排出量を削減でき、収集車が輸送する際に発生するCO2排出量の削減にもつながります。
・堆肥をプランターや庭、畑に利用できる
できた堆肥は野菜づくりに活用できます。微生物により分解された堆肥は、栄養が豊富。化学肥料を使用せずとも、土壌を健康に保ち、野菜づくりに大いに役立ちます。
また、日本は化学肥料の多くを輸入に頼っているのが現状です。食料の安定供給のためにも、有機物を肥料化・堆肥化し、広く活用することが、農林水産省により進められています。
・資源を循環できる
コンポストによって、生ごみが循環する資源へと変わります。野菜など生ごみから作られた堆肥を畑に入れて新たな野菜を育て、その野菜を調理するときに出た野菜くずは再び堆肥になります。こうした小さな循環をコンポストは生み出し、実践者が増えるとこの循環の輪をさらに広げていくことが可能です。
【参考資料】
コンポストとは? メリットや種類ごとの特徴、家庭での始め方を解説|朝日新聞デジタル
デメリット
このようなメリットがある一方、デメリットもあります。
・微生物が分解できない有機物(貝殻など)は入れないほうがいいものがある
・生ごみをコンポストに入れるための手間がかかってしまう
・悪臭や虫が発生する可能性がある
・堆肥を活用できる場所が少ない
「リジェネラティブ」とコンポスト
これまで食料の生産量を増やすため化学合成肥料や農薬、殺虫剤に依存してきましたが、それにより土中の微生物が減少、土が痩せてしまいました。国連食糧農業機関(FAO)によると、世界の土壌の33%が劣化し、土壌の侵食や栄養の枯渇、塩分上昇などの危機的な状況にあるといわれています。
堆肥は土壌を改善し再生する役割を担っており、堆肥を使うことで土の中で微生物が活発に働き、土壌の保水性と保肥性を高めてくれます。土壌を再生させ気候変動を抑えるコンポストは、リジェネラティブ農業にアプローチする有効な手段だと捉えることができます。
【参考資料】
「世界土壌デー(12月5日)」および「国際土壌年」開始に寄せる 事務総長メッセージ|国際連合広報センター
コンポストを実践する企業・農園の事例

コンポストを通して半径2kmの栄養循環づくりを推進|ローカルフードサイクリング株式会社
ローカルフードサイクリング株式会社は、家庭で手軽にできるコンポストで生ごみを循環させる「バッグ型コンポスト」の事業を手がける会社です。2023年度の利用者は23,252人にのぼり、558tのCO2を削減、1,137tの生ごみ削減を達成しました。
コンポスト導入へのハードルを下げるため、コンポストに関する疑問や質問をコンポストアドバイザー(NPO法人循環生活研究所認定資格)に無料で相談できるLINEサポートを実施。初めてコンポストに取り組む購入者は、約8割に及びます。
ローカルフードサイクリング株式会社が目指すのは「半径2kmの栄養循環づくり」。栄養を捨てず、地域内で活用することで、安心でおいしい食べ物が気軽に手に入り、地域の人が健康になる。そんなパブリックヘルスの実現を掲げています。
そのために展開する事業のひとつが、2024年に始められた「コミュニティガーデン」です。コミュニティガーデンは、地域に住む人たちで野菜を育てる場所でありながら、資源の循環拠点という役割も担います。自宅のコンポストで作った堆肥をもって来て野菜を作るなど、資源が循環する仕組みづくりが大きな目的です。このコミュニティガーデンを、2030年までに全国に1000カ所設置することを見据えた取り組みが進められています。
また「バッグ型コンポスト」を活用して、聖学院と女子聖学院の生徒たちが学校のサーキュラー化に取り組んだ事例があります。こちらの記事も参考にしてみてください。
【参考資料】
「捨てない暮らし」で、台所起点の食循環を|株式会社ボーダレス・ジャパン
半径2kmの栄養循環「ローカルフードサイクリング」とは |note【公式】LFCコンポスト
消費者と農家が連携したコンポストの取り組み|鴨志田農園
東京・三鷹市にある鴨志田農園は、質の良い自家製完熟堆肥を用いて、無農薬・無化学肥料による野菜作りを行っています。
農業資材として堆肥を活用するだけではなく、地域コミュニティーをどのように作っていくのかという視点からコンポストの循環に力を入れています。顔が見えない関係性になりがちな農家と地域の消費者が、日頃からつながっていくことが重要だと考え、農家と消費者が双方向の関係性を築くことを大切にします。
鴨志田農園は、CSA(地域支援型農業)を取り入れ野菜作りを行う農園です。CSAとは、農家と消費者が年間契約し、購入する農産物の代⾦を前払いすることで農業を支援するシステムのこと。鴨志田農園ではそこに、消費者がコンポストを通じて農家さんと関わることで、より強い関係性を作り出しています。
この取り組みではまず、消費者は地域の農家から野菜を買って、その野菜を使って出る生ごみを、自宅のコンポストケースで一次処理します。その後、農家が二次処理をして完熟堆肥にして野菜を作り、再び野菜を消費者へ届けます。これにより資源の循環も生まれているのです。
堆肥づくりにおいては「CNBM分類」という考え方に基づいています。CNBM分類とは、もみがらやおがくずなどの炭素(C)、米ぬかなどの窒素(N)、牡蠣殻や関東平野でよく出る赤土などミネラル(M)、微生物(B)の4つに分類し、配合すること。これにより60度の高温発酵ができ、1カ月かけて病原菌を消滅します。
鴨志田農園で行う堆肥化には、地域の20キロメートル圏内にある資源のみを使用する点も特徴です。たとえば牛糞や米ぬか、もみがらなどのように、その地域にある使用可能な資源を見定めたうえで使用しています。
また鴨志田農園では、熊本県南小国町の黒川温泉で、地域の生ごみから堆肥づくりに取り組んでいます。温泉街の旅館から出された生ごみを完熟堆肥に変えて、地域の農家に供給。作られた野菜は旅館で提供するという循環を生み出しました。
【参考資料】
サーキュラーエコノミー型CSA|AWRD(Loftwork Inc.)
鴨志田農園(東京都三鷹市)|農林水産省
堆肥作りは、料理作り。公共コンポストで地域を“発酵”させるサーキュラーエコノミー|IDEAS FOR GOOD

コンポストは、生ごみや落ち葉を資源に変え、自然に近い資源循環の流れを活かした取り組みです。生ごみの堆肥化に多くの企業や個人が実践し、出来上がった堆肥をうまく活用すれば、資源循環の輪を広げていくことができます。気候変動を抑制でき、環境を再生する確かなアクションにもつながるでしょう。
また、生ごみが分解される過程を観察することは、自然の循環を実感できる体験でもあります。この体験を、子どもの環境教育として活用するのもいいかもしれません。当たり前のようにある生ごみを資源と捉え活用してみませんか?
(ライター:藤野あずさ)
〈関連記事〉
企業の廃棄物削減 生ごみをコンポストで堆肥化する事例5つ